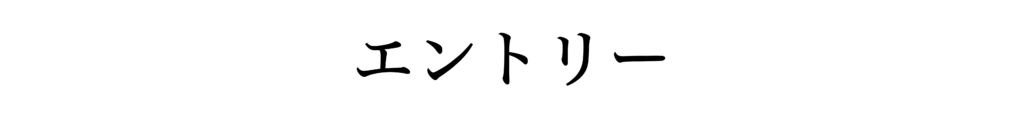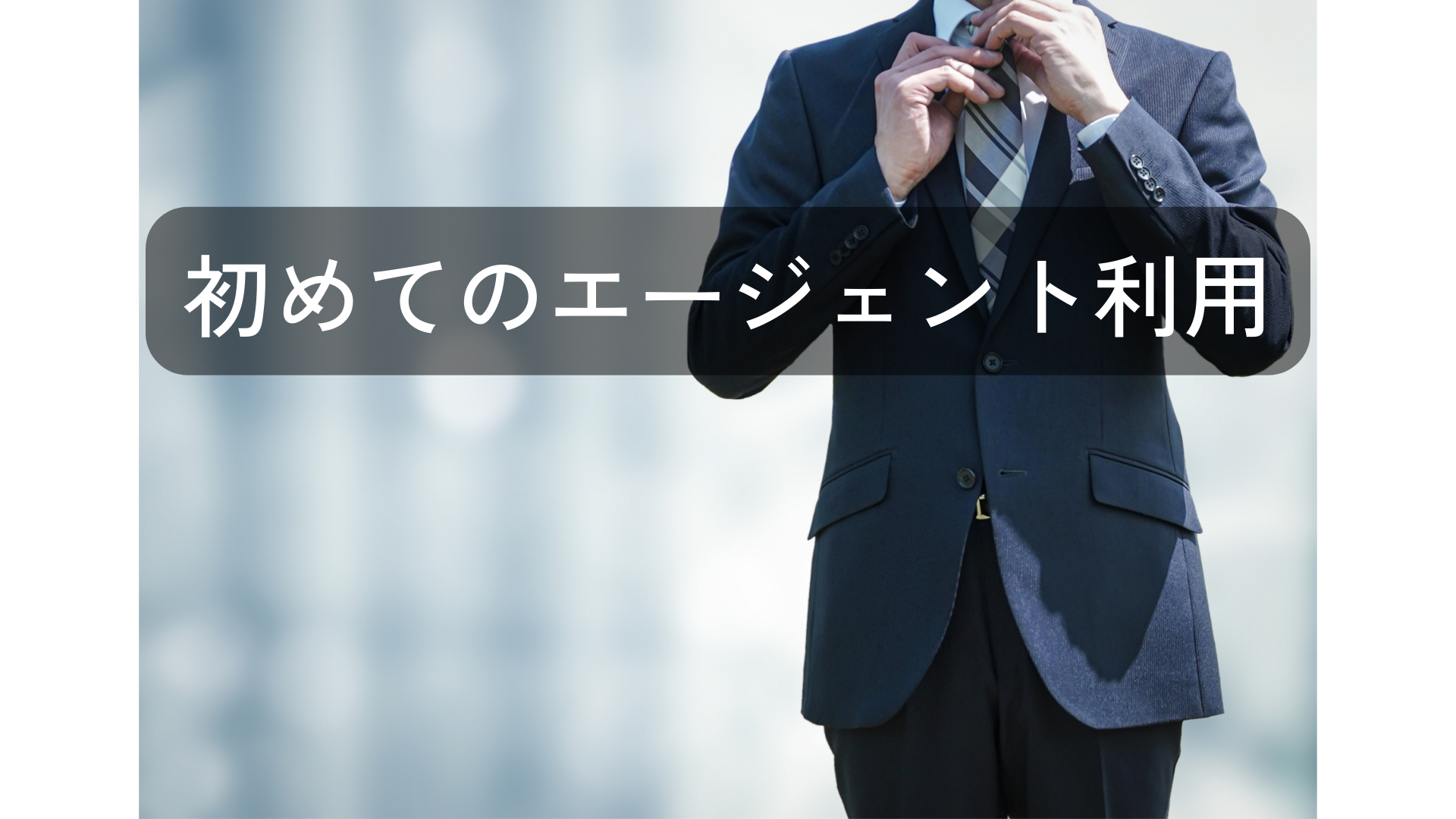この記事では、新卒入社1〜3年目(第二新卒)の方を対象に、初めての転職でエージェント利用をする際のポイントについて解説します。
転職エージェントとは、仕事を探している求職者と、求人を出している企業をマッチングさせる人材紹介業を行っている人たちのことです。(このブログを書いているSTORY CAREERも転職エージェントの一つです)
※ ちなみに第二新卒に関して厳密な定義はありませんが、一般に新卒入社3年目までの人のことを指すことが多いです。
まずは、新卒入社して3年以内に離職する人の割合を見てみましょう。
2021年10月に厚生労働省から発表された資料によると、31.2%と9年連続で30%を超える状況が続いています。
新卒が3年以内に離職する要因として多いのが、例えば以下のような理由です。
「入社前に聞いていた内容と、入社後の業務の内容が違っていた」
「実際に働いてみると、自分の価値観とのズレを感じた」
「職場の人間関係や残業の多さなどに耐えられない」
「今の環境よりもレベルの高いところにチャレンジしたい」
人によって、転職で求めている条件は変わると思いますが、自分に合った企業を一人で見つけ出すのは、なかなか大変です。おそらく0から探すと膨大な時間がかかってしまうでしょう。
その際に、転職活動の進め方や企業の求人の情報を得るために、転職エージェントの利用を考えている人も多いと思います。
以下では、第二新卒が転職活動をするうえで知っておいて欲しいことと、良いエージェントの見極め方をお伝えしていきます。
そもそも、企業が第二新卒を採用する理由は何でしょうか?
第二新卒は、新卒や中途の就職活動とはやや違った特徴があります。
まずは、4つのメリットから見ていきましょう。
- 新卒と違って一定の社会人経験があるため、初期の教育コストがあまりかからない
- 新卒と違って入社までに1年以上期間が空くということはなく、2~3ヶ月で入社できる
- 中途と比べて、企業文化に染まりきっていないので、自社の文化に馴染みやすい
- 他社に就職したがミスマッチで離職した優秀層に出会える可能性がある
一方、第二新卒を採用するデメリットは何でしょうか?
- 中途と比べて即戦力ではないので、一定の教育コストがかかる
- 企業側からすると、またすぐに辞めてしまうのではという懸念がある
企業によっては、第二新卒に対して「新卒」の要素を求めていることもあれば、「中途」の要素を求めていることもあります。
求人情報や面接を通して、求められるスキルや役割をしっかり確認するようにしましょう。
第二新卒の転職の難しさ
先程、第二新卒は新卒と中途とは違った特徴があるとお伝えしました。
結論から申し上げると、第二新卒の転職はある一部の優秀層を除くと「厳しい」のが現状です。
なぜかというと、
①新卒のように未経験からチャレンジ出来る企業が限られていること
②中途と比較したときに即戦力となりうる実力に達していないこと
が挙げられます。
それぞれ見ていきましょう。
①新卒のように未経験からチャレンジ出来る企業が限られていること
新卒では、商社、銀行、メーカー、コンサルなど、学生時代の経験によらずほとんど全ての企業に応募することができたと思います(あくまでも応募要件を満たしているかどうかの話です)。
しかし、企業によっては職務経験2〜3年以上を求めるケースや、第二新卒という枠を設けず中途採用の応募枠しかないケースが存在します。
結果として、新卒のときよりも選択肢は減っていると思ったほうがよいでしょう。
②中途と比較したときに即戦力となりうる実力に達していないこと
先ほど、企業によっては第二新卒枠がなく中途採用の応募枠しかないという話をしましたが、そうなると競争相手は、キャリアが自分より3年も5年も10年も上の即戦力のベテラン達です。
ほとんどの人が未経験だった新卒の就活と違い、中途採用ではそれぞれのスタート地点がそもそも違うのです。
エージェント目線で見た時の第二新卒の転職
ここまでで、第二新卒の転職の難しさをお伝えさせていただきましたが、転職が無理というわけではありません。むしろ、未経験の分野にチャレンジするチャンスであり、より自分に合った企業を選べる可能性があると見ることもできるでしょう。
転職の方法には、大きく分けて以下の4つの方法があります。
・自分で求人サイトなどを活用して応募する
・スカウト型のサービス(ビズリーチなどが有名)に登録する
・知人や友人から紹介してもらう(リファラル採用)
・エージェント経由で企業を紹介してもらう
今回は、特に4つ目のエージェント経由での企業紹介に絞ってお伝えします。
結論から申し上げると、「エージェント目線から見ると第二新卒は正直難しい」です。
理由は大きく2つあります。
①早期離職による退職をネガティブに捉えられる可能性があること
②経験年数や際立った実績がなく、書類選考に通りづらいこと
転職エージェントのビジネスモデルは、求職者を企業に紹介し、求職者が内定承諾をすることで理論年収の25〜40%がエージェントに支払われるというモデルになっています。
つまり、転職エージェントからすると、年収が高く、転職が決まりやすい(実績がある)人のほうが優先度が高くなります。転職においては、第二新卒の方の優先度は下がりやすい構造になっているということですね。
また、企業担当(いわゆるRA)と求職者担当(いわゆるCA)に分かれているエージェント(大手が多い)の場合、求職者に求人を紹介(マッチ)する仕組みとして、スキルマッチ・業界マッチ・職種マッチ、という経験ベースでのマッチングの仕組みが適用されており、スキルがまだあまりなく、業界や職種ベースでの転職ではないケースが多い第二新卒は、そもそもエージェントがマッチングしにくいという背景があります。
結果として、書類通過の確率が低く、結果的に20〜30社の求人に応募して書類通過したのが数社というケースも多く見受けられます。
良いエージェントを見抜くポイント
それでは、ここからは第二新卒の方に知っておいて欲しいエージェントを利用する時のポイントについてお伝えしていきます。
①1回の面談だけではなく、納得がいくまで真摯に向き合ってくれる
②企業によっては、自社推薦ではなく採用HPからの直応募を勧めてくれる
③エージェントの提携先以外の企業でも良さそうな企業を提案してくれる
④経験年数が不足していても、人柄など他のアピールポイントで書類通過してもらえる
通常、エージェントとは1〜2回しか面談する機会がないと思いますが、それだけでは分からない要素もたくさんあるため、エージェントの言葉を真に受けすぎるのも危険です。
また、本人のキャリアを考えた場合、マッチする企業が契約先ではない可能性も十分考えられます。その際に、他の選択肢(提携先以外の企業や、現職に残ることも含む)を提示してくれるかどうかは、エージェントを見るうえで重要な判断基準となります。
さらに、エージェントと紹介先企業との関係性にもよりますが、ギリギリ書類通過しないレベルの求職者の方の良い部分を引き出し、面談のチャンスを与えられるかどうかもエージェントの力量が問われるポイントです。
初めての転職エージェント利用-まとめ
いかがだったでしょうか?
この記事では、初めての転職を考えている社会人1〜3年目の方を対象に、転職エージェントを利用する時のポイントを解説してきました。
日本には2万社を超える転職エージェントの会社があると言われています。
自分に合ったエージェントと出会うためには、まずは3~4社のエージェントから話を聞いてみて、前述の基準などを参考にして信頼できそうなエージェントを選ぶことが重要です。
STORY CAREERでは、一人ひとりが自分らしいキャリアを歩めるように、求職者に真摯に向き合って複数回の面談を実施し、徹底的な自己分析をベースに企業とのマッチング精度を重視した転職活動を支援しています。
紹介先の企業数は決して多くありませんが、過去のサービス利用者や企業の採用担当者と強いリレーションを持っており、お互いの特徴や希望条件を詳細に把握したうえで選考のフォローをさせていただいております。
書類選考では、個人の経歴にもよりますが一部要件が不足していた場合でも、他の要素でカバーできるものであれば採用担当者と交渉して、面談実施までお繋ぎすることも可能です。結果として、今までに支援してきた方の書類通過率は95%を超えており、サービス利用者からも企業からも、自己分析とマッチング精度の高さに好評を頂いております。
STORY CAREERのキャリア支援サービスに少しでも興味を持っていただけた方は、下のエントリーフォームからお申し込みをお願いします。